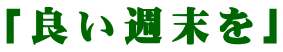
![]()
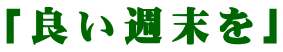
| 晩 夏 |
| 8月15日の終戦記念日とお盆がすむと、夏もいよいよ終り。 このお盆から8月末までの期間は、いわゆる晩夏の季節。 緑陰をつくる街路樹の通りを歩くと、それまでのアブラゼミの賑やかな蝉時雨に変わって、 カナカナゼミ(ひぐらし)のはかないなきごえをしばしば耳にするようになります。 その時、「今年も晩夏がやってきた」という感慨とともに、あの日、あの頃の、あの事を 懐かしく追憶するのです。 あの事とは、東京から奈良県の天理市までサイクリングしたこと。 時は、昭和44年(1969年)8月18日から22日までの4泊5日。 私が22歳の誕生日を迎える1か月余り前のこと。 昼は厚生省で働き、夕方から早稲田大学の第2文学部に通学していた頃で、大学4年の夏 休みの期間に職場での有給休暇を利用し、青春の思い出作りとばかりに、同じ職場の同僚 で理科大学に通学していたO君と一緒に出発しました。 私は当時、職場のバレーボール部の主将で、O君は卓球部の主将をしており、お互いに体 力・スタミナには自信があったのです。 しかし、街で見かける現代の若者たちが乗っている、スポーツ仕様の高機能のサイクリン グ車とは異なり、私たちの自転車は「実用自転車」。今でいうママチャリ(勿論、電動自 転車ではなく)。 現在のサイクリング車は、超軽量な車体で、坂道や高速に容易に対応できる幾つものギア が装備されていますが、私たちのは、変則ギアは全くない、普通の実用自転車。 急な坂道の登りも、高速可能な幹線道路も、ただただ一つのギアを回転させるために、必 死に重いペダルをこぐばかり。 これで、品川から東海道(国道1号線)を西に向かって黙々とひた走ったのです。 行程の概略は次の通り。 1日目は午後に日本橋の起点を出発。夕方早めに鎌倉に入り、知人の家で宿泊。 しかし、スタートした早々、横浜付近で私の中古自転車の後輪がパンク。 途方に暮れて自転車を引きづりながら自転車屋を探すも、皆無。 すると、ガソリンスタンドの前で「どうしたんだ?パンクか?」と、威勢のいいお兄ちゃ んが声を。私は頷きながら「このへんに自転車屋がありませんか?」と尋ねると、「ない ね。よっしゃ俺がなおしてやる。ちょっと見せてみろ」と言って、どこからかゴムやヤス リや接着剤を取り出し、手際よく修理をしてくれたのです。 時間にして20分ほど。 私たちはお礼を言って、なにがしかの料金を払おうとするのですが、「いいよ、いいよ。 気を付けて行って来いよ」と一言発して、byeとばかりに片手をあげて引っ込んでしまった のです。 そんな幸運なハプニングに見舞われた初日。 2日目は、鎌倉から沼津市へ。 茅ヶ崎、小田原、そして熱海へ。ここから十国峠を越えて三島に出るのですが、この行程 が難所続き。延々と続く砂利道の上り坂。時間は刻々と過ぎ、日も暮れてきます。 身体は炎暑と筋肉疲労でぼろ雑巾のようにクタクタ。 力果て、自転車を転がしながら坂道を登っていくのですが、「もう駄目かな・・。野宿す るか」との思いに何度襲われたことか。 だが「もう少し。もう少し」と言い聞かせ、日が 落ちた頃に三島へ。 それから沼津までは一気。 しかし、安く泊まれる宿を探すのが一苦労。 適当に何軒か当たるのですが、どこも満室や高料金で不発。 黒墨を塗ったような顔をして、当てもなく汗だくの姿で自転車を転がしていると、前方か らやってきたオジサンが「何しているんだい」と。 私たちが事情を話すと、「それなら私のところに来なさい」と言って先導。 到着したのは海岸近くの民宿。 料金を尋ねると、「いらんよ。ゆっくり泊っていきなさい。私は若い者が好きなんだよ」 と日焼けした顔に、笑みを浮かべるのです。 その夜はビールを飲み、旨い魚料理でご飯をタラフク食べ、食後は防波堤で夜釣りをする 人たちの釣果を覗きながら、涼しい潮風を満喫。 ただし、入浴が一苦労。 長時間の過激なペダル漕ぎで、お尻をサドルに強く擦りつけていたので、左右のお尻の生 皮がむけていたのです。 湯に触れると悲鳴が出るほど痛いので、仕方なく大きな浴槽の淵に両手をかけ、お尻だけ 湯面から出るようにうつ伏せで身体を浮かせて、入浴をすませました。 勿論、寝るときもうつ伏せで。 3日目は沼津から浜松へ。 この行程は距離があっても比較的に平坦で、快調に東海道を飛ばしました。 途中、富士のあたりで海岸に出て、海水で足や身体を冷やしてから、さらに松林と並行す る東海道を疾走していると、歩行者などの人影が全くない前方の道路沿いに、一人の若い 女性が立っています。 「こんなところで何をしているのだろう」と不審に思いながら近づくと、女性と視線が合 いました。 その瞬間、お互いにアッと驚嘆の声を。 「東井さん、どうしたの?!」 「小野さんこそ、どうしてこんなところに」 女性は大学のクラスメイトで、帰郷しているとのこと。 これから路線バスに乗って出かけるところだったのです。 そしてお互いに「また東京で」の言葉を交わして、別れたのです。 それからさらに自転車を飛ばしていくと、沿道に果物販売所がぽつぽつと立っています。 メロンやスイカなど。 ある小屋の前に差し掛かると、年配のおばちゃんが「ほれ、これ持っていきな」と声をかけてくれ、小ぶ りのメロンを手渡してくれました。 途中、それを割り、二人でかぶりついたのですが、そのみずみずしい甘さは、涙が出るほ どの旨さでした。 そして浜松に到着。宿泊は湖岸の国民宿舎。 朝の9時から夕方6時ごろまで、30分ほどの昼食と、道路沿いのドライブインで無料の お茶か水を飲むこと以外、一切休憩なく走りづめの行程。 お尻がサドルに擦れると激しい痛みが生じるので、走行中は殆ど腰を浮かせ、両足を立た せて疲れを軽減させていたので、宿につくとさすがに疲労困憊。 この夜も、布団の上にうつ伏せで寝ました。 4日目は浜松から名古屋へ。 この行程では、東海道を驀進する大型トラックに苦戦を強いられました。 当時(現在はわかりませんが)、東海道(国道1号線)は車道と歩道がガードレールなどで 明確に分離しているわけではなく、全て車道という感じ。自動車の通行の激しいところは、 自転車も車両として車道の路肩を細々と通行せざるを得ないのです。 そうすると、大型トラックが遠慮なく自転車のほんの横を疾走していくのです。 私は二度ほど、トラックの通過時の風圧で、路肩の下に転倒しました。 幸いどこもケガをしませんでしたが、恐怖感はありました。 名古屋へは夕焼け空の頃に到着。 私たちは伯母の大きな家で宿泊。 その日、年上の従兄をはじめ、伯母の家族中が私たちを歓待してくれ、遅くまで酒を飲み ながら身体の疲れを癒すことができたのです。 そしてサイクリング最終日の5日目。 名古屋から三重県の桑名、伊賀から笠置峠を越えて奈良市へ。 この行程も山岳地でタフなコース。 ここにくると私もO君もヨレヨレ。アップダウンの激しい道を幾つも乗り越え、最後はお 互いの距離が大幅に離れようが、声を掛け合いながら伴走することはなく、お互いの負け ず嫌いの根性丸出しで、抜きつ抜かれつしてひたすらに走行していました。 私は内心「いざとなったら、卓球部の練習より、バレー部のほうがきついはずだから、俺 が先に奈良公園に着いているだろう」と思いながら、O君に「先に行っているぞ」と声を かけ、一気に引き離し、両足を休めることなくマシーンのように強くリズミカルに回転さ せていたのです。 思えば、朴訥で芯の強いO君は、理数系の勉強は秀でていましたが、議論を交わすことは 得意ではなく、日頃から「我が道を行く」といったふうで、群れることはなく一匹狼的な クールさを内に秘めた男でした。 そして、いつもどこかに翳を抱いているような、虚しさを感じさせる男だったのです。 しかし、どういうわけか私とはお互いに心のどこかで「一目置く」関係としてウマが合い、 この年の前年には二人でやはり同期のI君の故郷・山形に行き、蔵王でスキーなどをしてき たこともあったのです。 私が奈良公園に着いてから20分遅れで、O君が到着。 彼は着くなり、近くの芝生にへたりこみ、「ああ、もう二度とこんなことはしないぞ!」 と叫んで、大の字になりました。 そして名古屋を出るとき、昼食用として伯母が持たせてくれたおにぎりを荷台の袋から出 すと、むさぼるように食べ始めたのです。 昼食は時間を稼ぐために、途中の売店で菓子パンと牛乳だけですませ、おにぎりには手を 付けなかったのですが、これがミスでした。 「おい、食うのはやめて早く天理に行こう。叔父さんの家ですき焼をたらふく食べようぜ」 と言っても、「これを食わしてくれ。もうもたん」と、夢中で食べているのです。 それから30分後。 午後7時半ごろに叔父の家に到着。 叔父には6時頃に着くと前もって言ってあったので、叔父さん一家は準備万端、まだかま だかと待っていたのです。 汗まみれの私たちは、風呂よりまずはビールでも飲んで、すき焼を腹に入れて落ち着こう と食卓につき、乾杯。 だが。 私が「やれやれ、やっと完遂した。さて、ご馳走になるか」と意気揚々にビールを干し、 すき焼の肉に箸を入れたとき、O君が急に「痛い・・腹が痛い・・・」と言ってうずくま ったのです。 私たちは驚いて、「ビールで冷えたんだろう」「胃が疲れているのかな」などと口々に言 いながら、彼の様子を心配しているが、痛みはエスカレートする一方。 余りの痛がりに、叔父さんが「病院に連れていったほうがいい」と判断したので、私は彼 を何とか連れて、近くの総合病院の夜間救急窓口へ。 当初は赤痢を疑っていたが、診断は大腸炎。 あの、朝に作ったおにぎりが、サイクリングの自転車の荷台で1日炎天下にさらされ、腐 食したためと判断。 彼は1日病院に入院し、翌日退院。そして翌々日、私と一緒に新幹線で帰京したのです。 車中、真黒でげっそりとした顔の0君に、「最後の最後で災難だったな」と慰めると、 「もう二度としたくない・・・。 絶対に嫌だ。でも、楽しかったけどな」と苦笑。 私は、窓外に波打つ稲穂の田園風景や、その上に広がる水色の空を眺めながら、「もう夏 の終わりだ」と、一瞬センチメンタルな気持ちになりました。 今でも、晩夏の季節が来ると「何であんな旅をしたんだろう」と思い出すことがあります。 そして「あの程度なら、どうってことはない。自転車が良ければ楽勝だった。面白かった」 という思いと、「あの年齢だからやれたのだ。もう少し年を取っていたら、やらな(やれ な)かっただろう。きつかった」という思いが交叉します。 やりたいと思った時が、やれる時とは限りません。 やりたいと思った時は、すでにやれない心身の年齢の場合が、往々です。 いずれにしろ、あの1969年の夏は、あの21歳の時の晩夏は、とても暑くてエキサイ テイングでロマンチックだったことは、確かです。 ちなみに、O君はその後、大学卒業と同時に千葉の南房総の海沿いの故郷に帰り、地元の 高校の数学の教師になりました。 生徒たちにも評判がよく、同居の老いた両親の面倒を見ながら、課外活動にも熱心な先生 だったそうです。 その彼は、サイクリングから4年後の25歳の時、交通事故で早世しました。 彼は彼なりに、25年の歳月を精一杯に生き抜いたのだろう。 そして、その中のたった5日間のあのサイクリング旅行のことを、いつか思い出したこと もあったのだろう。 今年の晩夏も、喫茶店の一隅から、そんなことを考えてみるのです。 「The way we were」 それでは良い週末を。 |