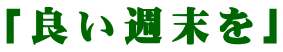
![]()
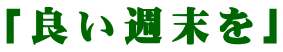
| 緑 陰 の 人(上)
|
|
西日本豪雨災害の被害状況が報道されたとき、そこに甚大な被災地の一つとして愛媛県宇 和島市の名前があった。 日頃から滅多に聞かない市名だったが、この時は何となくテレビの画面を注視した。 そして、Gさんのことを数十年ぶりに想い出した。 Gさんは、私が通学していた早稲田大学の第二文学部(夜間部)のAクラス(1年〜2年) のクラスメートだった。 Gさんは出身が宇和島で、色が白い清楚でおしとやかな女性だった。 1年から2年まで同じAクラスで一緒だったが、30数名のクラスの半分以上が女性で、 どの女性も綺麗で洗練されていたが、その中でもGさんは地方出身の目立たない地味な性 格だったが、その優しい人柄がにじみ出ている素直な表情の美しさは、際立っていた。 私が、そんな彼女と親しくなり始めたのは、20歳になった4か月後、昭和43年の早春、 大学2年の終わりの頃だった。 私は、当時の記憶を辿りながらこう書いてきたが、「そうだ!」と急に閃き、書棚の隅に 置いてある古い日記帳を取り出した。そして、その中からGさんの名前が書いてある箇所 を拾い上げてみた。 その一部を転載したほうが良い、と思ったからだ。 70歳となった現在の記憶では、当時の20歳の拙い思考と未熟な行動を、それでも真夏 のような情熱とときめきに満ちていた青春時代の1ページを、いまここにリアルに表現で きないことは、明らかだからだ。 それでは、日記の一部を少し省略して記してみます。 ・昭和43年(1968年)2月14日(水) 「ライトへ行く途中、不意にGさんのことを思いついた。 (注・早大界隈の喫茶店。ちなみに、大学周辺から高田馬場駅近辺までのエリアで、頻繁 に使った喫茶店は、フェニックス・オリエント・ライト・早苗・ブルボン・らんぶる・白 鳥・アイン・ローリエ・明治茶房など)。 学部の事務所で彼女の住所を調べ、道で人に2回尋ねたらすぐに見つけられた(注・文学 部のキャンパスからほど近い、鶴巻町の叔母の家に同居していた)。 勇気を出してドアを開け、娘さんが出てきたので、呼び出してもらう。それが慌てて「G さんをお願いします」と頼んだものだから、同姓のご主人(叔母の夫)が間違えて出てき てしまった。不在だったので、丁寧に礼を言い、帰り始めたら、途中でそこの叔母さんと Gさんとが、向こうから歩いてくるのに出くわした。一瞬ドキッと緊張し、さりげなく話 しかけていく。 「いま、君のところを訪ねたばかりだよ。こちらお母さん?」 あがっていたので、失礼な言い方をしてしまった。俺は横で叔母さんがいぶかしげに見つ めているので、余計緊張してしまい「ん・・ちょっと、ここの辺を通ったから。寄ってみ ようかなと。ちょっと話したいことがあって。・・・6時までに行かなくてはならないと ころがあるんだけど、いま暇?」 Gさんは咄嗟に「あとで・・電話をしてください・・・」と、静かな声で言い、あの神秘 的な、化粧を施してない美しい顔に微笑を浮かべて、俺を見つめてきた。 俺は長居はまずいと思い、ぎこちなく礼をしてその場を退散した。やけに恥ずかしい後味 であった。だが、歩きながら「これで良かった」と思うようになってきた。 良かったのだ。まず実行することだ。思いつめた後には」 ・2月15日(木) 「Gさんに電話した。受話器を取ったのは彼女だった。昨日のことを喋り、色々なことを 喋った。彼女は自分のことを内向的だと卑下していた。僕は彼女に、後日ダベリ合おうと 提案した。彼女も賛成した。 その後しばらくして、彼女から職場(注・私が勤務する厚生省統計調査部)に電話があっ た。「先ほどは、叔母さんがそばにいたので、旨く喋れなかったの。それでいま、外の電 話ボックスからかけています」とのことだった。叔母さんはものすごく古風で干渉するの で、娘さんも困っているとのことだった。 結局、成績発表日(注・学年末の成績表の手渡し)の午後5時半に、文学部事務所で会う ことにして切った。すばらしい余韻が胸に渦巻いている」 ・2月21日(水) 「午後5時半に事務所前でGさんと待ち合わせる。先に自分の成績表を受け取る。 まあまあ、めでたしめでたしだったが、彼女は半を過ぎても来ない。 かっかりしてスロープを降り始めていると、彼女が校門をくぐって駆けつけてきた。 それから、フェニックスで3時間ぐらい談笑する。はじめは緊張して、舌が思うように動 いてくれなかったが、だんだんと気安く冗談を交わしたり、茶道、旅行、恋愛の話などに 熱中してしまった。さりげない化粧顔の中に、みずみずしい美しさが溢れている。 9時になったので、彼女の学割をもらいにスロープを一緒に上り、事務所まで行った。 人影はなく、夜空一杯に星が輝いて美しかった(注・このスロープは、坂本九が歌ってヒ ットした「見上げてごらん夜の星を」の舞台。作詞した永六輔は第二文学部出身)。 別れ際、再会を約束し、お互いに微笑みながら別れた。 素晴らしい人だ、と心の中でも微笑みながら」 ・2月24日(土) 「午後1時にGさんと記念会堂前で落ち合う。 早めに来すぎたので、政経学部の受験生でごった返す、寒風の構内を彼女とブラブラ。 清楚に着飾った美しい日本的な彼女。 高田馬場の日活に「黒部の太陽」を観に行ったが、3月1日からの封切なので少し落胆し、 日比谷へ。界隈をぶらついて結局、スバル座の「いつも心に太陽を」を観る。 場内ムンムン立ち見で足が疲れたが、それ以上に映画の面白さに感動し、疲れを忘れた。 黒人青年教師の真剣で一途な授業姿勢に心を打たれた。 観終えて、パーラーに行き、ジュースとホットドックを食べながら、ダベった。 そして華やいだ気分で皇居前の寒風を縫って、東京駅に出て、それから馬場に。 彼女は遠慮していたが、家まで送っていった。駅前からもバスに乗らず、ダベりながら歩 いた。初春の夜のロマンチックな帰り道。 彼女は人に送ってもらうのは、ひどく悲しくなるから嫌いと言っていたが、俺が帰省の際 は駅まで送って行ってやると言ったら、承知した。 3月1日に東京駅に。 彼女に何か目に映せない魅力を感じて、引っ張られていく。 彼女は言った。「地味なもの、静のもの、明より陰のものに惹かれると。活発な明るいも のに共鳴する反面、その反対のものに惹かれる」と・・・・・。 俺もそのような思いを持っている。 例えば恋愛と、結婚は、一致しない場合があると。 強烈に惹かれる人との恋愛は生じやすいが、必ずしも結婚の相手とはならない。 たいして魅力は感ぜず、ときめく恋愛は生じなくても、結婚生活ではこのような人とのほ うが上手く行くはずと。有名人や諸先輩の例を見ても、そう感じる。 明るいものに親密感、好感を感じる反面、陰のあるものにひどく惹かれる。 人間の心には、両者が存在しているのだろう」 ・3月1日(金) 「午後4時20分ごろ、Gさんから電話があった。本当は4時に電話してくる約束だった ので、おかしいと思っていたが、今日、不意に、下宿の叔母さんが東京駅まで送って行っ てあげる、と言ってきかなかったとのこと。 俺はちょっと気落ちし、落胆したが「きっぱりと言ったら・・・・、きっぱりと、友達が 見送りに来てくれるから・・・と」。 「それが出来たらいいんですけど・・・。感情を害してしまうのが恐ろしくて・・・。本 当にどうしたら・・・」 俺も、額から汗が滲んでくるし、どうしたもんだと思案して電話口で躊躇してた。 すると、彼女は「もう当分会えないわね・・・」と沈んだ声を。 「どうしようか・・・」 瞬時に考えた末、叔母さんを見計らって一寸の間、抜け出て、丸の内側の中央口で会うこ ととし、電話を切った。 午後5時半から7時半の発車まで、ゆっくりと話ができると思っていたのだが。あの叔母 さんには、全く困ったものだ。 憎むより呆れるほかなかった。 中央口で約束の5時半前から待っていた。 心配だった・・・。来れるかな・・・・と。 半を過ぎたら、Gさんが向こうから駆け足でやってきたので、ほっとした。 俺の住所を教えた。彼女のもそこで書いてもらった。 「今度いつ戻ってくるの?」 「そうね、26日頃の予定だけど・・・」 「そしたら、その時に電話くれない」 「そうね、すぐするわ」 「26日からだって、まだ休みがあるんだから、鎌倉かどこかへ行こう」 「そうね・・いいわね」 つかの間の短い会話だったが、彼女に会えて本当に良かった。 そして、お互いに手紙を出し合う約束をして、別れた。 その後の寂寥感。無性にどこかをブラつきたかった。誰でもいいから誰かと滅茶滅茶ダベ りたかった。(後略)」 その後の日記には、Gさんの名前が出てこない。 代って、激化する大学紛争、職場のバレーボール部の試合、職場の年下の女性のことなど が記され、5月24日(金)付では「大江健三郎の「見る前に跳べ」を短時間で完読。彼 の大学時代における精神の気象が解かれる気がした。学問とセクスと自我・・・・。この 絡み合わせが生む事実。 俺自身は、ただ見ているだけで、飛ぼうとしてない様なこの頃・・・」 そして、3か月半ぶりにGさんの名前が出てくる。 この空白の時期、Gさんと会っていたのかどうか、全く記憶がない。 ・6月14日(金) 「Gさんから昼休みに電話があった。俺は初めは誰かな?と思って受話器を握ったが、ど うもクラスのGさんの様な気がしなかったのだ・・・。 「次の日曜日あいてますか?」「うん。別に何もないけど」 「そしたら、ちょっと青山の美術館まで来ていただけませんか?」「上野の?」 「いえ、青山ですけど」 「俺、知らないんだけど・・・。一体何で?」 「ちょっと、ご相談したいことがあるんです」 意味深な口調が気になった」(注・結局待ち合わせ場所は、早大の記念会堂前になった) ・6月17日(月) 「昨日の日曜日は、Gさんと記念会堂前で会い、生協の前の屋上で雨上がりの太陽光線を 浴びながら、相談事を聞いた。 彼女の現在は、あの叔母さんに従属させられ、親切を通り越したいやらしい監視のもとに、 束縛された生活となっている。このままでは自我が捻じ曲げられ、この尊い青春の時期も 枯れてしまうのではないかと悩んでいるとのこと。その解決策として、その家を出るとか、 昼間に外に働きに行くとか、脱出を考えたが、叔母に強引に辞めさせられた。またそのよ うなことを言おうものなら、露骨に嫌な顔を見せるとのこと。 俺は、それでは叔母さんに不愉快な気持ちをズケズケ言う勇気を持ったらと促したが、彼 女は、それで言いたいことを言ったら、毎日顔を合わせるので、気まずい思いになって生 活が耐えられなくなる、と俯いてしまった。 俺はわからない。彼女が叔母さんの性格を緩和しようと努力しても、駄目だろう。また、 耐え忍べなどと残酷なことも言えない。やはり、本当に自我の成長、自由の獲得を望むの なら、風当たりが強くなろうとも、勇気を出して言うべきだろう・・・。 しかし、その家の実情を知らない俺が、評論家的な正当論を述べても無責任になるし・・・。 しばらくやり取りをし、結論が出ずまま、俺たちは気分転換に目白台にあるカテドラル・ 聖マリア大聖堂に行った。 市谷台からいつもジュラルミン色に輝く、翼のような幾何形を眺望していたが、目の当た りに見ると、そのスマートで均整の取れた荘厳さに圧倒された。 さすが丹下健三の設計だけある。 彼女とダラダラ坂を下っていくと、行く手に白や茶色のチャチな住宅やビルがひしめき合 っているのが眺望できた。 カラッとした青空にスジ雲が浮かび、周囲の緑樹が何とも美しかった」 ・6月18日(火) 「紫陽花の花が一輪、机上に置かれている。 薄紫と、いまだその色を持ちえない黄緑の花弁の集まり。 紫陽花は初夏の細々と降る雨に濡れてこそ、その美しさが増す。 雨に濡れて美しい花では、これが一番だろう。 Gは、「花で一番好きなのは、紫陽花だわ」と言った。 俺は、この花は嫌いな部類に入れていた。 はっきりしない。湿っぽく、ぼたぼたした大輪が性に合わないのかもしれない。 そして開花期が梅雨時なので、爽やかなイメージを持てないから。 彼女に「この花の花言葉を知ってるかい?」と尋ねたら、「気まぐれ。浮気・・・」 「あまりいい言葉を貰ってないな・・」 彼女は「花の色が変わるからでしょうね」と言って、花房を白い指先で優しく撫でつけて いた」 ・6月20日(木) 「Gに対する印象が、なぜこうも変わるのだろう。 日曜日には、俺が好きだといった紫のツーピースを着て、薄く化粧を施した清楚な顔で、 つつましやかに振舞っていた。 でも昨日は、ピンクのサマー・セーターを着て、いたって軽装で晴れやかだった。 とても感じが良く、美しかった。 俺はやはり、溌溂としたフレッシュ感を持つ女性に惹かれるのか。 Gと観に行った映画「鳥」と「ミクロの決死圏」は長蛇の列で、館内はムンムンしていた。 ヒッチコック監督の「鳥」は、余りにもショッキングで、彼女は時々「ああ」とか溜息を 出して目をふさいでいた。 外に出ると小雨が降っていた。彼女は家に傘を取りに帰り、俺にピンク色の傘を貸してく れた。 その傘をさして、高田馬場までの歩いていく気恥ずかしさと、踊るような心・・・。 途中、クラスのTさんが、あの聡明でしっかりした彼女が、見知らぬ男と相合傘で談笑し ながら俺の前でバスを待っていたが、彼女は俺に気づいたろうか。ピンクの傘をさしてる 俺に。 俺は傘を斜めにして顔を隠しながらバス停を離れて、歩き始めた。 前方に、Sが傘をささず、雨に濡れながら歩いていた。革マル(注・過激派)に傾倒して いる最近のS。 雨に濡れて行く彼の背面に、寂寥感と傲然としたものが漂っていた」 この日記に記帳していた頃は、本格的な夏の到来を間近に控えた時季。 成人になったばかりの私は、昼は厚生省統計調査部の仕事、職場での組合活動、バレーボ ール部の練習、そして夕方4時半に退庁し、徒歩で早大文学部のキャンパスがある早稲田 に。 キャンパスの中では色々な講義を聴き、休憩時間はクラス委員としてクラス討論を行い、 キャンパスを出ると、毎晩のように誰彼なしに、喫茶店や飲み屋で政治論や文学論や恋愛 論をダベっていた。 しかし、そうした連中とは離れ、いつも決まった女友達と静かに行動して存在感の薄かっ たGさんは、我々とは異質な、まさに世間知らずの綺麗なお嬢さんでしかなかった。 「しかなかった」とは悪い意味ではなく、それだけ当時でもピュアで汚れを知らない、貴 重な存在の人と解釈したほうが妥当。 今のような嘘とエゴと欲望と自己主張が激しい時代では、まさに「絶滅種」でしょう。 いま、こうして日記帳の断片を記していると、この年の真夏に、日比谷公園の小音楽堂周 辺に聳えていたプラタナスの大樹の木陰のベンチで、白いワンピースを着たGさんが、静 かに本を読みながら私を待っている姿を想い出します。 私は、吹き出る額の汗を拭いながら、しばし遠くから彼女を眺め、何か映画のワンシーン を観ている錯覚に陥っていました。 そして、この人は「緑陰の人」だと思ったのです。 以下は、次回に。 それでは良い週末を。 |