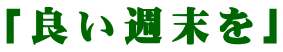
![]()
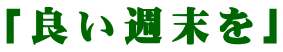
| や す ら か に
|
| 白球は、光が乱反射している真夏の青い空に虚空を描き、高々と外野に跳んだ。 外野手が、足首まで伸びた夏草が繁茂している外野のグランドを、よろけながら背走して 白球を追いかけている。しかし、白球はわずかに外野手が伸ばしたグローブの上を抜けた。 私は、「本塁、本塁!」と大声を出して、右手をぐるぐる回した。 1塁と2塁の走者は、勢いよく塁間を走り、それぞれ息せき切ってホームインした。 「よしっ、やったぞ!」 私は右手のこぶしで手のひらを叩き、ホーム・ベースに駆け寄った。 ゲーム・セット。 サヨナラ逆転勝利だ。 試合後、双方のチームがユニホームを着たまま、1塁側の草地で缶ビールを立ち飲みして お互いの健闘を称え合った。 この時は、すでに敵も味方もなく、同じ仲間として和気あいあいと交わっていた。 誰もが灼熱の太陽の光を浴びながら、黒く日焼けした顔に爽やかな笑顔を浮かべていた。 私は「厚生省ブルーバッカス」の監督兼プレーヤーとして、U法人チームのF監督と缶ビー ルをカチッと合わせて乾杯し、乾ききった喉に冷えたビールを流し込もうとした瞬間・・・・。 目が覚めた。 「夢か・・・」 時計を見ると午前5時だった。 閉め切った雨戸のわずかな隙間から、薄い光が部屋に射し込んでいる。 私はほのかな薄明りに浮かぶ部屋の天井板を、布団に横たわったまま、まんじりともせず に見つめていた。 夢の内容は、私が39歳、昭和61年頃のこと。 原宿の日本社会事業大学のグランドで行った、Uチームと私共のチームの親善野球試合の こと。 U法人は、健康増進関係の調査研究事業を主事業とする団体で、創設から日も浅い財団法 人だった。 当時、私は厚生省保健医療局企画課で、公益法人の指導監督を行う係長の職にあった。 所管する45法人の、決算等の会計処理や事業計画の策定・実施の適正化などを指導する ほか、定款等の一部変更認可、後援名義の可否、特定公益増進法人の認定そして公益法人 の設立認可にあたっていた。 ちなみに、私が在籍した2年間で、(財)日本股関節研究財団、(財)日本リューマチ財 団、(財)老齢健康科学財団の設立を認可し、他課所管の(財)エイズ財団の設立認可申 請等、2〜3の新設にもかかわっていた。 そうしたことから、様々な多くの法人関係者とのご縁が生まれ、今日まで続いている方も 少なくない。 U法人は、トラバーユしてきた専務理事のFさんが、実質的に動かしていた。 彼は私と同じ年齢だったが、人の懐に飛び込んで親しくなる術を持った、ある種の野心家 であり、アイデアマンでもあった。 しかし、法人運営の知識には全く素人で、事業計画や予算案の立案、特定公益増進法人の 基準や、そもそも公益法人の趣旨というものに無知で、誤謬が多かった。 そこで、しばしば私のところを訪れ、指示を仰いでいた。 理事会などにも指導の一環で出席した。 Fさんの一途で熱心な法人活動への取り組みが進み、洒落た会報の配付により、法人の名 も徐々に広く認知されるようになってきた。 そして、Fさんが意外と素直で単純で裏がない人であることを感じていた。 そんな頃の野球の交流試合だった。 彼も私も、経験と知識と情熱に自信が持てる年齢になっていた。 私は半分眠気と半分正気の頭で、天井を眺めながら当時のことを懐かしく回想していた。 傑作だったのは、グランドで缶ビールを飲み終え、皆が着替えをし始めた時、私は大声で 「表参道に出て、どこか銭湯を見つけて入浴しよう!そのままの格好でいいから、行こう!」 と発破をかけ、全員、汗泥のユニホームとスパイク姿にスポーツバッグをぶら下げて、ぞ ろぞろと街中に出発したことだった。土曜日午後の若者でにぎわう竹下通りをぶらつき、 周囲の怪訝な表情をよそに明治通りに出て、数人の先行隊を走らせて銭湯(公衆浴場)の 探索に。 結果、表参道交差点の裏の、住宅街の一角に古風な銭湯があり、みな嬉々として一番風呂 に飛び込んで汗をながした。さらに、マネージャーに、この近辺の飲み屋を探させたとこ ろ、すぐに開店間際の大衆酒場を発見。両チーム一体となって、遅くまで飲んで騒いだこ と。実に奔放で愉快なひと時だった。 Fさんとは以降、他の2人を誘った4人1組で、私が会員の茨城県友部にあるゴルフ場に、 平日ゴルフに行っては、ホールアウト後、駅前の居酒屋で乾杯し、帰りの常磐線特急「ひ たち」の中で、沈みゆく太陽を眺めながら缶ビールを飲み、さらに上野駅で外に出て、繁 華街のカラオケ店で飲んで歌って騒いだりすることが、定番となった(経費はすべて各自 精算と割り勘。私が私費でおごったことも多々)。 そんな日々が、私が厚生労働省を早期退職し、三重に赴いた56歳(2004年)までの ほぼ15年間続いた。 勿論、Fさんはそうした友人・知人の中の一人、ワン・オブ・ゼムであったが、きっと彼 も私も、あの15年間は自信に満ちた、愉快でエキサイテイングな時期だったと思った。 しかし、私が三重に単身赴任して三重県厚生連の役員として日々を忙殺されている間、F さんからしばしば電話があり、私が帰京した折に喫茶店で落ち合い、彼から法人の実情を 聞かされた。 一言に集約すると、「財団の財政がひっ迫していること」「そのため、関西のサービス業 を営んでいる某氏の資金援助(寄付金)を受け、見返りに理事職(理事長?)ポストを用 意する予定であること」 それから、風の便りでU法人にとって芳しくない話が聞こえてくるようになった。 そして私が59歳の時、ある日曜日の夕方、三重に戻る新幹線に乗車する前のひと時、品 川駅構内の飲食店でビールを飲みながら彼の話を聞いた。 U法人は乗っ取られ、理事長以下全理事が交代して変更登記されていること。Fさんは一 方的に解任され、事務所のカギも取られて中にも入れない状況であること。乗っ取り組は Fさんが「法人の金を横領している」との虚言を流布し、Fさんを横領の罪で告訴し、一 方で厚生労働省に着々と自分たちの活動ぶりを報告し、既成事実を作り始めていることな ど。 私はFさんに、「弁護士をたてて、彼らを詐欺・横領・公文書偽造・名誉棄損等で訴えて 戦うべし。貴方の名誉のために」と助言。 翌年、私は東京に戻った。 株式会社を設立して「健康酒」の製造・販売事業を行うために。 Fさんは縁のある弁護士をたてて、東京地裁での裁判に入っていた。 私は喫茶店で、彼にこれからの戦いの進め方を助言したり、裁判資料の下書きの修整など を行った。 だが、法人の事務所を乗っ取られ、法人からの給与が途絶されたFさんは、全く収入の当 てが無くなり、生活は困窮の一途を辿っていた。 私の事務所を訪れた時、「バス代が勿体ないから、歩いてきましたよ」とカラ元気を見せ、 居酒屋で会ったときは、「金は私が持つから」と前置きして酒を飲んだが、彼は「酒なん て何ヶ月ぶりかな・・・」と、しみじみとして杯を運ぶ姿に、私は「この裁判は、是が非 でも勝たないと・・・」と他人事ながら痛感した。 裁判中、Fさんから2、3度借金の依頼があった。 どうにもこうにも生活費がひっ迫して困っていると。 私はすぐ一緒に銀行に行き、ATMで新人サラリーマンの月給ほどの金を引き出して手渡 した。 それぞれ後日、何回かに分割されて返済された。 そして。 裁判が始まってから数年後、判決が出た。 法人の乗っ取りが断定され、Fさんの原状回復が認められた。 だが、乗っ取り組は事務所の引き渡しを遅延し、全てを引き継いだ時には、当初の基本財 産が殆ど消えていた。 そこで、Fさんは乗っ取り組・虚偽の理事たちを相手に、損害賠償請求の裁判を起こした。 その頃、裁判費用などもろもろの経費調達のため、彼から私に再度金銭の借用依頼があっ た。 この額は、新人サラリーマンの手取り年俸額ほどだった。 私は「たとえ友人間であっても、金の貸し借りで友情が壊れるどころか、相手が憎い敵に もなる。だからけじめだけはしっかりしよう」と直言し、返済計画を明記した借用書を提 出させ、金を振り込んだ。 毎月〇万円の返済としていたが、それは数か月でその半分になり、すぐに1万円となった。 その頃から、私はFさんとの関係に距離を置き始めた。 彼も金のことで悩んでいることだろうと推察したが、私も悩んでいた。 「もう返済はいい。今の裁判に専念して頑張ってくれたらいい」と、いつ切り出すかと。 そして彼との縁を切ろうと。 そう決心していた矢先の昨春、Fさんが突然、私の事務所を訪ねてきた。 「いままで、ありがとうございました。法人の収入(寄付金)の当てが出来たので、残り の金を一括返済させていただきます。確かこの額だと思います。今の裁判に勝ったら、ま た何がしかの金額をお返しします」と言って、封筒を手渡された。 私は彼に対して「よくやったね」とは言わず、久々の笑顔を作って無言でそれを受け取っ た。 だが、封筒に書かれた数字は、私が振込通帳で確認していた残りの額より、はるかに足ら ない額だった。 しかし、内心で「一度はあげようと思った金。もうこの努力だけでいい」と思い、しばし 沈黙していた。「これから弁護士との打ち合わせがあるので、これで失礼します」と立ち 上がった彼の手を握り、「頑張って」と声をかけて別れた。 あの日から、Fさんからは一度も電話は無く、また会うこともなかった。 私は「縁は繋ぐばかりでは駄目。切ることも必要」と、心のどこかで考えていたのかもし れない。 彼にはこちらからも、一切連絡をしなかった。 彼は「東井さんは私のことを避けている」と思い込んでいたのかもしれない。 今月1日、私は71歳の誕生日を迎えた。 その夜、ふっとFさんのことを思い浮かべた。 「私も彼も71歳。どんなに騒いでも、残された歳月は限られている。だからもう、取る に足らないこだわりは捨てて、残された人生を晴れ晴れと共に生きるのだ」と考えた。 そして、近いうちにU法人の事務所を不意に訪れてみよう。彼はどんな顔をするだろうか。 きっと喜んでくれるに違いない。 そんなことを想像していたら、身体が熱くなり、ブルッと震えたりした。 だが・・・。 10月14日の朝。 携帯電話が鳴った。 こんな朝に誰からだろう、と携帯のSMSを見たら、U法人の評議員のWさんからだった。 メールにはFさんが10月12日に逝去された旨が、手短に書かれていた。 私は事務的にWさんとメールをやり取りし、終わってからしばし呆然としていた。 その後、葬儀関係のFAXが届いている青山の事務所に向かった。 悲しみも驚きも、浮かんでこなかった。 だが、電車に揺られているうちに、じわじわと空虚感が沸き上がってきた。 悲しいとか泣きたいとかの感情ではなく、「むなしい」感じだった。 身体は脱力感に覆われていた。 そして、「なぜもっと早く、訪ねてやらなかったのか・・・」という悔いが心を震わせた。 先日の野球の夢は、きっとFさんが俺に天上から送ってきたものだろう。 「東井さん。あの頃は本当に楽しかったなあ・・・・」と。 Fさんは一緒に電車に乗ると、座席で私にもたれてすぐに寝てしまい、到着駅でも起きな いので困り果てたことがあった。冬のゴルフの帰り、4次会で私の家に来た時、炬燵に足 を入れるやすぐに横になって寝てしまい、結局身体に布団をかけて泊まらせたこともあっ た。 今はただ、こう言ってあげられる。 「もういい。もう頑張らなくてもいい。よく走ってきたよ。俺はそう認める。もうゆっく り寝たらいい。やすらかに・・・・」 |