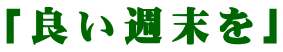
![]()
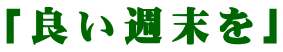
| 夢の中へ
|
| 眠りから目が覚めた時、一瞬「ここはどこだ?今は何時(いつ)だ?俺は幾つだ?」と思 った。 しかし、見慣れた木目の天井が目に入るや、これも瞬時に「ああ、家だ。結婚して家族が いるんだった。今は年とったオヤジだ。もう学校や職場に行く義務が無いんだ」と思い、 ホッとした気分になった。 そして、しばらく床についたまま、布団のぬくもりに浸っていた。 これは、正月2日の朝のこと。 まだ眠りから完全に覚めやらぬ脳裏に、背番号55の左打者が鋭くスイングする姿が残っ ていた。 私は天井を見つめながら「これは何の初夢だ?」と、ぼんやりと考えた。 「あれは松井秀喜選手?いやダボダボの上下白のユニホームだったし、 スイングは鋭い けどコンパクトに振っていたから違うな。あれはやはり川上だ。それにしても川上の16 番ではなく、55番とは・・・」 前夜の寝しなに観た、昭和24年の10月に公開された、白黒映画「野良犬」(監督・黒 澤明)の一場面であることは確か。 主人公の刑事(三船敏郎)が、真夏の炎天下の後楽園球場で、ホシ(殺人犯)にピストル (コルト)を密売した男を、先輩刑事(志村喬)と二人で張っている場面。 超満員の球場はワイシャツ姿に白い帽子の観客ばかり。当時の男たちの誰もが、外では帽 子をかぶっていた習慣があったことに驚いた。 試合は「巨人対南海」。 内野席の最上段から、志村がせわしなく扇子をあおぎながら、球場を眺めて呟く。 「すごい人だねえ。どのくらいいるかなあ・・・」 すると、白の夏服の背広に白い鳥打帽を被った三船は、タオルでしきりに顔の汗を拭いな がら「5万はいますね」と、野太い声で返答。その間も双眼鏡でくまなく観客席を眺めて いる。 球場にアナウンス嬢の声が響く。 「4番ファースト川上」 超満員の球場が、大きく波打ってどよめく。 左バッターボックスに立った川上は、サイドスローの投手が投げた初球を、バットを身体 に巻き付けるように、鋭くスイングして白球を叩き返す。見事な左中間のヒットで、走者 が二塁から生還。 そう、川上哲治選手は当時からの巨人の主軸打者で、一世を風靡し、後に巨人のV9を達 成した名監督。 その川上の黒い背番号16の文字が、白一色の超満員の球場と、ぎらぎらと照りつける白 い熱光の中で、目に焼き付くように鮮明に映った。 試合は昭和24年の夏に開催されていた。 私がまだ2歳になる数か月前のこと。 私の目は、敗戦直後の東京の記録映画を観る感じで、画面を興味深く凝視していた。 映画の随所随所に、当時の闇市やガード下にたむろする、復員兵や浮浪者やパンパン(売 春婦)や米兵に抱き着いて歩くオンリーや、特攻上がりのヤクザらの姿が克明に活写され、 焼け跡に建てられた掘っ立て小屋での庶民の極貧の生活が映し出されていた。 そして街角からは、アメリカナイズされた快活なリズムの中に、妙に物悲しさを秘めた 「東京ブギウギ」や「リンゴの唄」が流れていた。 それらの生活困窮者・戦争被害者らの退廃的で疲弊した情景と対照的に、この後楽園球場 の溢れるほどの明るい活気は、別世界のように映った。そして時間と空間を異にする70 年後の私も、この球場の庶民の雰囲気に同化し、これも一瞬のことであるが、心をときめ かせて見入った。 そして映画は終わる。 あれから70年ほどの歳月が流れ、テレビドラマなどでは刑事・警察物の作品が数をなし ているが、この「野良犬」は、まさに刑事物の元祖であり、今も魅力が失せていない傑作 だと思った。 そのワン・シーンに使われた巨人の川上(私の住んでいる上馬の隣町、野沢に自宅があり、 一度、近くで車椅子に乗っている姿を見かけた)。 これらの映画の場面が混然として私の交感神経を刺激し、余韻冷めやらぬうちに就寝した ので、冒頭の様な夢を見たのだろう。 それにしても、なぜ背番号16が55になっていたのか? 私はそろそろと起床し、着替えをしながら思った。 原因はきっと、3つの「55」が脳内にインプットされていたからだ、と。 まず一つ目。 映画での川上の姿を、松井に重ね合わせて観ていたからだろう。川上は中距離ヒッター。 松井はロングヒッター。 だから二人のバットが描く線はやや異なるが、両者の打席での威風堂々とした自信に満ち た構えや、軸足の左に重心を置いたブレのない、力強いスイングは驚くほど似ていた。 映画では川上の後姿だけしか映っておらず、顔の印象は全くなかった。その後姿だけを 「これは松井選手を見るようなドキドキ感があるな」と感じながら見つめていたので、自 然に松井のイメージがかぶさってしまったのだろう。 私の記憶にあるのは、巨人の左の大打者は、川上→王→松井。これだけなのだ。 二つ目。 寝しなに入浴し、上がってから体重計に乗ったら「55キロ」。 「今年も55でスタートだな」の感を強くした。 この日(元旦)は朝から夕方まで食べて飲んだのだが、それでも体重は55キロ。昨年は ゆで卵一つしか食べない日や、モーニングにトースト一枚と珈琲1杯食しただけの日も、 55キロだった。 「食べても食べなくても55キロとは、これいかに?」と苦笑した。 この数値は、最近7年間ほど殆ど変化なし。 20〜50代前半の頃は、常に63キロ前後。三重に赴任した56歳から60歳までは、 新たな職場と初めての単身生活という環境の変化と、月2回の東京との往復などで59キ ロに。60歳で帰京し、会社を設立・経営した67歳までは、にんにく酒の製造・販売で 奔走し、57キロに。 そしてその後は、仲間と法人を設立して楽しく交遊を深める日々が続いているが、体重も 55キロで継続。食事量が年なりなのだろう。 この程度の体重が、一番調子が良いようだ。 毎日、風呂上りに乗る体重計の表示が「55」。 これが7年間続いているので、「55」が脳裏に残っているのかもしれない。 三つ目。 新年になってもコロナ自粛が続く今日この頃、毎日ぼんやりと晩酌をしていると、決まっ て頭に浮かぶことがある。それは「今年は高校を卒業してから、55年になる」という思 いだ。 卒業したのは1966年(昭和41年)の早春。 18歳で皆と別れ、それから、それまで生きてきた歳月の3倍の時間が過ぎ去ったのだ。 感慨が酒の美味さをいやます。 良き仲間、良き恩師、スポーツや文化活動の盛んな校風、そしてのどかな自然環境。私は 良き環境の中で、自由闊達に3年間の学園生活を送ることが出来た。これは、たった一度 の人生の中で、二度とない得難い青春の日々だった。 今振り返ると、つくづくそう思う。 だからといって、「もう一度あの頃に戻りたい」とは思わない。 「人生が二度あれば」という人もいるだろうが、私にはそれもない。 たった一度だから、たった一度のチャンスを生かせたからこそ貴重なので、それで今日が ある。 悔いのない人生は、やり直しをする必要が無い人生なのだと思う。 そして、良き思い出は、生きている限り永遠に不滅なのだ。 「卒後55年」を考えながら、当時の楽しかった思い出をたどり、忘れがたき友やガール フレンドを思い浮かべる時、55年の時を超えた今でも、彼ら彼女らが当時のままに、若 い笑顔で私の前に出現する。 いずれにしろ、「55」の初夢でスタートした令和3年。 今年は日本も世界も、今までにない混迷の年になる予感がします。 良いことも悪いことも、幸不幸も、国際関係も景気も人間関係も、全てが「五分五分」に なることを、ただただ祈るばかりです。 不安な時や、悲しい時や、辛い時や、苦しい時は、「夢の中へ」行ってみましょう。自分 の心の中には、意外と素晴らしいものが輝いていると思います。 それでは良い週末を、良い一年を! |