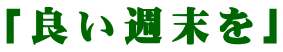
| 花屋の前で(2) |
| 「この人は、一人暮らしの生活困窮者だろうか。3月といえどもまだまだ肌寒い薄曇りの 日に、薄着で素足のままサンダルをひっかけた格好をしている。適当に茶菓子を食べたあ と、ブラブラとこの辺を散歩しているのだろうか。それにしても、東京の下町ならまだし も、この辺りではまず見かけない姿だ・・・」と、私は瞬時に勝手な想像をしながら、花 屋の店先の花々を眺めていた。 この辺りというのは、ビルの1階にあるこの小さな花屋の場所である、皇居前の千鳥ヶ淵 公園や国立劇場が目と鼻の先である「隼町」を中心として、その周辺は麹町、紀尾井町、 一番町、二番町などの高級マンションやオフィスビル、日本テレビやFM東京や、幾つもの 大使館や学校やホテルが立ち並ぶ、まさに都心部なのだ。 それが、普段着のまま、近くの豆腐屋に小鍋を持って下駄を突っかけて買い物に行くよう な、そんな下町風情だった。 店の前の鉢植えの花は数が少なかった。お得意先は、きっと近くに散在している国会議員 の事務所や、ホテルや劇場やパーテイ会場への御祝いの花卉や花束だろう。ガラス越しに 見た店内は、様々な大小の胡蝶蘭の鉢で埋まっていた。 それでも春の日の夕暮れに眺める、店先の小さな花々は可愛いくて綺麗だった。 おばさんは「きれいねえ。この花は何ていう花かしら・・」と、私に聞くともなしに呟く ので、私は「このピンクの花はナデシコで、そっちの赤い鉢植えの花はゼラニウムかな」 と言うと、「まあ、よくご存じですね。私は花が好きなんだけど、何にもわからないんで すよ」と言われた。 顔を見ると、色白の肌は小皺がいくらか見えたが艶があり、頭髪の半分以上は白髪混じり だが、小ざっぱりとしていた。 小柄な体つきだが、何かしらの品が漂っているように見えた。 話し相手がいないので、何か話をしたかったのだろうか。それとも元々が気さくな性分で、 若い頃は快活で人気者だったのかも知れない。いまになって、そんな想像が浮かんでくる。 「私が知っているのは、せいぜい300円ぐらいで売っている、小さな鉢植えの花ぐらい なんだけどね。花屋で適当に2、3個買って、庭先に置いとくだけですよ」 「まあ、いいわねえ」 「おばさんとこも、庭に色々な花が咲いているんじゃないの?」 「私のとこは庭が無いの」 「マンション?」 「いえ、一戸建てだけど、庭が無いの」 「おばさんの家はどこにあるの?」 「そこよ。すぐ近く」 「だって、このへんはビルばかりじゃない。普通の住宅なんて見たことないけど」 「昔から残っている家が、私の家の周りにも3軒あるわよ」 私は、この人は近くの地元の人ではなく、もう少し市ヶ谷か九段方面から来た人と思って いたので、まだ半信半疑だった。 「そうなんだ。それならどこかに別荘でも買えば、たくさん花が植えられるじゃない。だ けど、経済的に大変だからなあ・・」と、素っ気なく言うと。 また、否定語で平然とこうおっしゃった。 「いえ、おカネはあるの。経済的には心配ないのよ」 「失礼ですが、旦那さんは何をなさっているの?」 「主人は裁判所の判事だったの。私は横浜に住んでいたけど、主人と結婚してここに移転 してきたのよ。ここは最高裁判所などが近いでしょ。だから昔からここに住んでいるの。 私の息子達もみんな弁護士で、この辺りのマンションに住んでいるのよ」 「そうか。それでこの半蔵門に住んでいるんだ。確かに最高裁もすぐそこだし、高裁も地 裁も弁護士会館も、三宅坂を下ればすぐだからね。いや、ご家族が法曹界の人ばかりとは、 たいしたもんだなあ・・」 「私は、横浜のコウジョに通ってたのよ」 ここから、おばさんのコウジョという単語が何回も出てきた。 でも私はふんふんと分かった振りをして頷いていたが「ところで、コウジョって、高等女 学院とか高等女学校とか言うんですか?」 「そうなの。ダイイチ高女」 「ダイイチ?横浜市立第一高等女学校とか?」 「そうですよ。第一高女には岸さんもおられたわ」 「えっ?あの女優の岸恵子さん?」 「ええ、あの方は私より2学年先輩だったけど、優秀な方でしたよ」 「私も岸さんのエッセイや小説を読んだことがあるけど、女優としても作家としても一流 ですよね。ご一緒でしたか」 「岸さんは、先生たちから優秀だと褒められていましたよ」 「岸さんは、確か今は90歳ですよ。今年の8月に91歳になられるけど、まだまだお元 気で綺麗ですよね。そうか、するとおばさんは、今年で89歳になられるんだ。まいった な。おばさんもお若い」 私は80代前半のおばちゃんだと思っていた。 (注・帰宅して、本棚の「女優 岸惠子」(キネマ旬報社)を開いて調べてみた。すると 年譜に「1945(昭和20)年4月、神奈川県立横浜第一高等女学校へ入学」とあり、 彼女の書中のエッセイには「バレエが大好きで、第一高女を卒業するまで通い続けた」と いう箇所があったので、ダイイチコウジョの通称は、横浜市、いや神奈川県内では普通だ ったのだ。ちなみに、第一高女は、1900年(明治33年)に、神奈川県で最初の県立 高等女学校として創立されており、その後、県内でも優秀校として評判だったとのこと) 私は、おばさんに「いや、花もいいが、おばさんの話も面白かったな。私はこれから帰り ますけど、ご自宅まで送りましょう」と言うと「すぐそこなんですよ」と、元気にスタス タと先導された。 花屋からほんの100メートルほど。細道を曲がってすぐのところに、高層建築に囲まれ た小さな石柱の門があり、その奥に、タイル張りの2階建の大きな古い佇まいが見えた。 磁器の表札には、昔の山の手の邸宅でよく見かけた、「弁護士」という楷書の黒文字で書 かれた肩書が、添えてあった。 私は、おばさんに軽く会釈して別れた。 そして「あの人は浜っ子かも知れないが、今や、古き良き時代の東京っ子だな」と感心し た。 そんなこんなを思い出していたのが、先週の今日。6月7日(水)の、半蔵門にある花屋 の前でだった。 その前の週にも、私の地元である三軒茶屋の花屋の前で、ちょと嬉しい出来事があったの です。 その続きは、次回にでも。 それでは良い週末を。 |