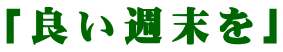
| 夏がゆく(6) |
| 1966年(昭和41年)8月、私は、オホーツク海沿いのサロマ湖に近い北海道紋別郡 上湧別町の母の実家を訪ねた。その日から5日目のことだった。 それまでの間に、叔父の運転で遠軽町に住む叔母二人(次女・4女)と共に、上湧別から 1日で行ける名所をドライブして回った。 車は、ちょうど4人が座れる中古の小型車で、確かトヨタ自動車初の大衆車として、 1961年頃に発売されていた「パブリカ」ではなかっただろうか。 でも、前席は運転席の叔父だけで、叔母二人と私は後席に詰めて座った。 叔父が「悪いけど、助手席は開けて、後ろに三人で座ってくれないかね。誰かが座ると、 ハンドルをとられて危険なんだわサ」と苦笑いして言った意味が、車が走り始めてすぐに わかった。 当時は、草道や泥道や砂利道や岩道ばかりで、アスファルトの道は極く稀にしかなかった。 車は信じられないほどエンジン音を鳴り響かせ、ゴトゴトと上下左右に激しく揺れまくっ た。これは東京では、いや私が行った日本各地でも、今日に至るまで全く経験したことが ない、ワイルドなドライブだった。 車で巡ったのは、阿寒湖、摩周湖、屈斜路湖そして美幌峠などだった。 既にこれらの名所は小学生の頃に社会科の地図で習い、北海道の観光案内の写真でその姿 を承知していたが、実際の光景を目のあたりにした時は、その荘厳な自然の佇まいに素直 に感動した。 景色はどこも風光明媚の一言に尽きた。 雄大な原野は明快な美だが、湖と峠の起伏が織りなす壮大な景観は、まさに美麗の一言だ った。 翌日は、三女にあたる叔母に会いに、オホーツク海沿いの興部(おこっぺ)町に行ってき た。 この小さな町は、オホーツク海沿岸の極地である北の宗谷岬と東の知床岬を結ぶ海岸線の、 ちょうど真ん中に位置する湧別町から、少し北へ上がった所にある。 当時の時刻表(昭和42年3月1日改訂版)を見て気づくのだが、私は名寄本線の「上湧 別」駅9時35分発の名寄行きのデイーゼル機関車に乗車し、「興部」に11時12分に 到着したはずだ。 所要時間は約1時間40分。 線路はずっと海岸沿いを走り続けた。右は海で左は平原だった。 その間は、数人しか乗客がいない車内の右側の席に座り、どこまでも広がるオホーツク海 を飽きずに眺めていた。 これほどの自由無碍に広がる壮大な海のパノラマに遭遇し、それも1時間以上も見とれて いたことは、今日まで唯一無二、空前絶後のこととなった。 現在では車窓の右側に見えるオホーツク海は不変だが、左側の陸の部分はだいぶ風景が変 わったことだろう。もう一度乗ってみたいが、石狩本線は平成元年(1989年)に廃線 となってしまった。 そして冒頭に述べた、母の実家に滞在して5日目のこと。 私は叔父に連れられて、上湧別からすぐ近くの(と言っても車で10分ぐらいの)サロマ 湖に行った。 天気は薄曇りで空は灰色によどんでいた。 サロマ湖(佐呂間湖)は、琵琶湖・霞ヶ浦に次いで日本で3番目に大きい湖であるが、汽水 湖では日本最大である。 汽水湖とは海水と淡水が入り混じった湖沼で、他に浜名湖や宍道湖などがある。 サロマ湖は、オホーツク海の湾入部が、堆砂によって海と仕切られた湾湖。 しかし、オホーツク海と考えたほうがいいだろう。現に2つの湖口があり海と繋がり、潮 が満ち引きしている。 私と叔父は、サロマ湖に着くと、しばしその海を見ていたが、ほんの小さな砂浜にボート 屋が開いていたので、ボートに乗ることにした。 ボートは5艘ほど置いてあり、ボートに乗っている客は1組だけだった。 季節的に北海道の夏は終わりで、そろそろ店をたたむ頃なのだろう。 ボートは私が漕いだ。それまで東京でも、井之頭公園や洗足池や外濠(そとぼり)などで 貸しボートを漕いでいたので、慣れていた。 叔父は漕いだことが無く、ボートの先に座ってニコニコしていた。 ただ、やはり「海上」の様子は池とは違った。 公園の池や外濠などでは、水面の自然の波は全く気にならなかったが、サロマ湖では、水 面が盛り上がってうねっている感触で、一種の生き物のように感じた。オール(櫓・ろ) を漕ぐにも、その自然と言う生き物を相手にしているので、少し緊張し、水の質量が濃密 で重いので、倍の力がいった(注・塩水が混じっているから少しは浮力があるだろう、な どとという推測は間違い)。 それでも腕には自信があったので、両足で舟底の板を押し蹴り、上半身を背筋を使って後 ろにそり返しながら、思い切り左右の腕と手首を使ってオールを操り、ボートを進めた。 叔父さんも気分良さそうに、はるかかなたの水平線を眺めていた。 私も大気は冷たかったが、それが心地よく感じられ、爽快な気分で漕いでいた。 しかし、そうした愉悦の時間は10分ほどで終わった。 それまで薄曇りだった空を、黒い雲がにわかに覆い始め、辺りが暗くなり、強い風が吹き 始めて波立ってきたのだ。 するとポツポツと雨が降り出してきた。 叔父さんが「天気が悪いから引き返そう」と言ったので、私は舟先を急遽、沖合から砂浜 に変えてオールに力を入れた。 だが、強い波風にあおられて進まない。それどころか、気がつくとボートはどんどん沖合 に流され、岸が遠くに離れて行くのがわかった。 波風が高くなり、ボートは左右に大きく揺れてきた。ヘタにオールを漕ぐとバランスを欠 いて転覆してしまう状態に陥っていた。 私は左右のオールをなるだけ均等に広く開き、大きな波が引いて小波になった瞬間に全力 で慎重にオールを操っていた。 しかし、ボートはどんどん沖合に流されていった。 叔父さんは真っ青になり、肘を伸ばした両手で左右のボートの縁を抑え続けながら「助け てくれー!」と湖岸のボート屋のおじさんに届くように、叫び続けた。私もオールに集中 しながら「おーい!」と叫び続けた。だが驚いたことに、砂浜にはボートが全て裏返しに 干されているだけで、誰もいなくなっていた。 空には不気味なほど黒い雲が立ち込め、寄る辺のない暗い荒れた海が広がっているだけで、 すがるものは四方八方に人一人の影どころか、木っ端の一つも何もなかった。まさに私た ち二人は、すべてが自然のうごめく世界に放り出され、孤絶していた。 風も波も雨粒も勢いを増してきた。 頭の中は真っ白になっていた。 一瞬「これで大波に襲われたら完全に転覆する。死んでしまう・・・」と、生まれて初め て「死」ということを心底からリアルに意識した。 だが、今から思うとそれも瞬時のことだった。もはや「死ぬ」という恐怖心さえも吹っ飛 び、ただ「今の生きている状態」を守るためだけに、本能的に身体は夢中でオールを漕い でいたのだ。まさに一秒一刻が勝負だった。1分後も5分後もなかった。 いま改めて思い起こすと、この時ほど「生きる」という、人間としてこの世に生まれてき た者の究極の命題を、理屈抜きで身体全体の本能で体現していた。そうした体験はこれま での人生でも、他に一度もなかったように思う。 叔父は、青ざめた表情で身を固くし、叫ぶのもやめて両手で左右のボートの縁を握りしめ、 少しでもボートが大きく傾くことを防いでいた。 その表情には、私と同様にもはや「観念」の境地にあるか、あるいは私と同様に、何も考 えられない頭が真っ白の状態にあったのかも知れない。 私の腕は既に棒のようになり、顔から身体中まで汗で濡れ切っていた。 半時間ほど、ぶっ続けで神経をとがらせ全力で漕ぎ詰めていたので、もう身も心も限界に なってオールを横にしたまま、少し深呼吸をした。 それはほんの10秒ほどの束の間だったが。すると急に我に返り、無意識のうちに心の中 で「神様、助けて下さい・・・」と何度も呟いていた。 「死への恐怖」ではなく「生への望み」だったのだろう。 もはや死ぬのは時間の問題だろうが、最後の最後でこの大地を包含する宇宙の偉大な何か 「サムシング・グレート=神様」に叫び続けてみよう、という直感が生まれ、そうさせた のだった。 私は、心の中で「神様・・・神様・・・」と唱えながら、荒波と格闘を続けた。 すると、驚くばかりの事態が生じた。 急に、黒雲で覆われた空から、微かに陽光が射し込んできたのだ。 そしてあれほど強く吹き荒れていた風が急に途絶え、波しぶきも徐々に小さくなってきた。 「あっ、風がおさまってきた!!」 叔父も私も交互に空を見上げ、歓喜の声を上げていた。 空には、薄い黒雲が勢いよく次々と流れ去っていた。 私は蘇ったように、岸辺に向かって力一杯オールを漕ぎ続けた。 帰りはウソのようにオールが楽で、進行が早かった。 砂浜に着くと、何事もないような顔をしたボート屋のおじさんが、再びボートを並べ始め た。 その態度に、よろよろとした足取りでボートを降りた叔父は「人が助けを求めているのに、 さっさと後片付けをして引っ込んでしまうなんて、無責任じゃないか!」と、何度も怒り をぶつけていた。 私も「あんたね、カネを取ってボートを貸しているということは、同時に管理責任もある んだよ。ボートの客がどこにいるかぐらい、監視してなくては駄目だよ」と叱ったが、お じさんは「ハア・・ハア・・」と下を向きながら頷いているばかりだったので、私たちは その場を立ち去った。 あの場合、救助の船もモーターボートも無く、もし警察や消防署に救助を求めても、出動 してくるのは1時間以上かかり、本格的な救助はボートが沈没して遭難の恐れが確認でき てからだっただろうが。 私と叔父は、疲労困憊していたが徐々に生気を戻し、近くの小さな古いラーメン屋まで歩 いて行った。 誰も客がいない店内の奥に、小上がりの畳部屋があり、そこでビールを飲んだ。叔父は先 ほどのボート屋をひとしきり非難した後、また二人で黙々と飲んだ。そして叔父は、よう やく笑顔になって「ああ、死ぬかと思った。助かって良かった・・・」としみじみと呟い た。 私も同様だった。 「それにしても、よく助かった」という実感は、その後に徐々に湧き起こってきたが、ま だビールを飲んでいる時は心身が興奮しており、私には乏しかった。まさに何か悪い夢を 見ていて、急に息苦しくて目覚めた時の心境に似ていた。 「ああ、怖かった。あれは夢だったのか。良かった・・」と。 実家に戻ってからの夕食時も、叔父はその時の話を短くしたが「助かって良かったサ」と、 余り家族に余計な心配を与えないようにし、その実、コップのビールを飲むたびに、安堵 の溜息を繰り返していた。 だが私は後年、いや今日に至るまで、あのサロマ湖の奇跡は忘れてはいない。 翌朝、帰京の途につくため、私は叔父・叔母、そして祖父・祖母に感謝の弁を述べ、母の 生まれ育った実家を発った。 玄関口の馬の背を撫でて、めんこい馬にも別れを告げた。 北の果ての壮大な大地にも別れを告げた。 駅まで送ってくれる車の窓から振り返ると、まだ祖父もこっちを眺めて手を振っていた。 私は急に涙がこぼれそうになる衝動を抑え、実家に来た時から一度も顔を見せなかった、 突き抜けるように青い大空に目をやった。 「今度来るまでに、必ず、涙をみせない逞しい成人になっているからね」 そう誓った。 19歳の夏もゆき、来るべき新たな季節が始まろうとしていた。 だが、あの時の決意は、まだゆき過ぎてはいないのだ。 そんなことを追憶しながら、76歳の夏がゆきすぎようとしているのです。 それでは良い週末を。 |